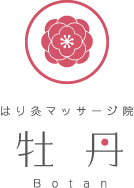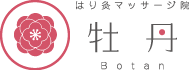2025.09.14/東洋医学
日本鍼灸の地図帳と人はなぜ治るのか

自然治癒力について考えたくて、アンドルー・ワイルの「人はなぜ治るのか」を再読。
“少は多より大なり”という無限小の法則を読むと、微量な刺激で全体を調整することができる東洋医学に共通するものを感じて面白かった。治癒は“強制”ではなく“誘発”されて起こる。
東洋医学のことをかなり褒めているけど、同時に現在は“純粋で力強い哲学”とは程遠いものになっている、と言っていてすごく印象に残ってる。手引き書医学はめっちゃ痛烈。
『現在でも、施術者の大半は理論の理解が浅く、したがって、理論を直観的・練達的な治療の基盤として駆使できずに、確固とした信念を欠く、いわば「手引き書医学」になっているふしがあるのだ』
ポモ族のシャーマン、エシー・パリッシュの治療の説明が鍼灸師みたいだと思った。
「手の力を使うときは、そうだねえ、釣り糸を垂れて魚が引くときのように、ちょうどあの引きの感じみたいだ。それがわかるのさ。ググッと感じるんだよ。その人のからだのどこかに隠れている痛みが、手をグッと引っぱるのさ。だから、必ずわかる」
松田博公先生の松塾スペシャル「日本鍼灸の地図帳」がめちゃくちゃ勉強になった。
日本に来た文化は「実感主義、単純原則志向、理論嫌悪、実利主義」といった方向に変容する、という指摘は日本鍼灸を考える上で重要なポイント。按摩や漢方、気功、太極拳にも共通しますよね。
日本鍼灸は「中心が2つの楕円」だという説明も初めて聴いた時は感動した。学生の頃からの謎が解けたような気持ち。僕の中にも日本要素と中国要素があって、楕円が常にぐにょぐにょと変形してるような感覚があるかも。