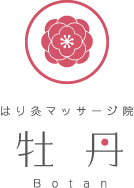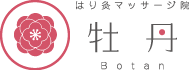2025.04.20/東洋医学
Kiriチーズアイスと日本鍼灸を求めてⅣ

石川橋のファミマで、Kiriのクリームチーズアイスを見つけた!
シャリシャリしたシャーベット状いちごピューレとKiri100%チーズのこってりした風味がメチャクチャ合いますね、、
チーズのアイスが大好きなので、これは何度もリピートする!

松田博公先生の対談集「日本鍼灸を求めてⅣ甦えるいのち」がディープで読みごたえがあって、いい書籍を読んだという感動。
このシリーズは巻末の“あとがきにかえて”がメチャクチャ面白いんです。今回のテーマは「無心」という、技芸が到達すべき究極の境地。
爲さんという全盲の按摩師のお話がしびれた。
山本有三の「無事の人」という文庫に収められたお話です。戦中の旅館で、爲さんが療治しながら語った内容。なんかメチャクチャ刺さった。僕の実家が旅館だったので、鍼灸マッサージ師の専門学校に入る前は、こういう按摩師さんになりたいと思ってた気がする。
「わっちってものがなくなっちゃって、ただじねんのお計らいにまかせる。それが手あての一番のかなめなところでござんしょうね」
深谷灸法の「ツボは硬結」として捉えるシンプルさがまさに日本鍼灸。
「おおづかみに身体を捉えて、滞りを取り除けば全体の気血は流れ、自然治癒力が活性化して病は癒えるという考え方。これは日本的発想だと思います」
福島哲也先生が紹介していた奇穴の注夏(ちゅうか)は僕が好きなツボ。合谷の手のひら側にあるので、深谷灸法では裏合谷と呼んでるらしい。合谷を指圧する時は、合谷と注夏の間にある小さな球を挟むような意識で圧してる。
鈴木眞幸先生の黄帝内経の読み方が面白い。「臓腑名経脈の呼び方は、経脈とは何かという本来の考え方自体を危うくさせる」という視点は、今まで持ったことがなかった、、
経穴という点を繋いだ線が経脈ではない、というのは僕もそう思ってる。もっと複雑で、多層的で、ダイナミックな気のルート。
素問の疎五過論篇には「患者の社会的な挫折体験や鬱屈した心理を把握しなくてはならない」といった内容が述べられている。地位が高かったが勢力を失った時に「脱栄」という疾病が起こるそうです。肉体と心の病を区別してないのがすごい。
まずはこの本で何度も取り上げられてた左合昌美さんの「よくわかる黄帝内経」を読まなくては。プレミアがすごいし、図書館にもないけど、、なんとか手に入れたい。